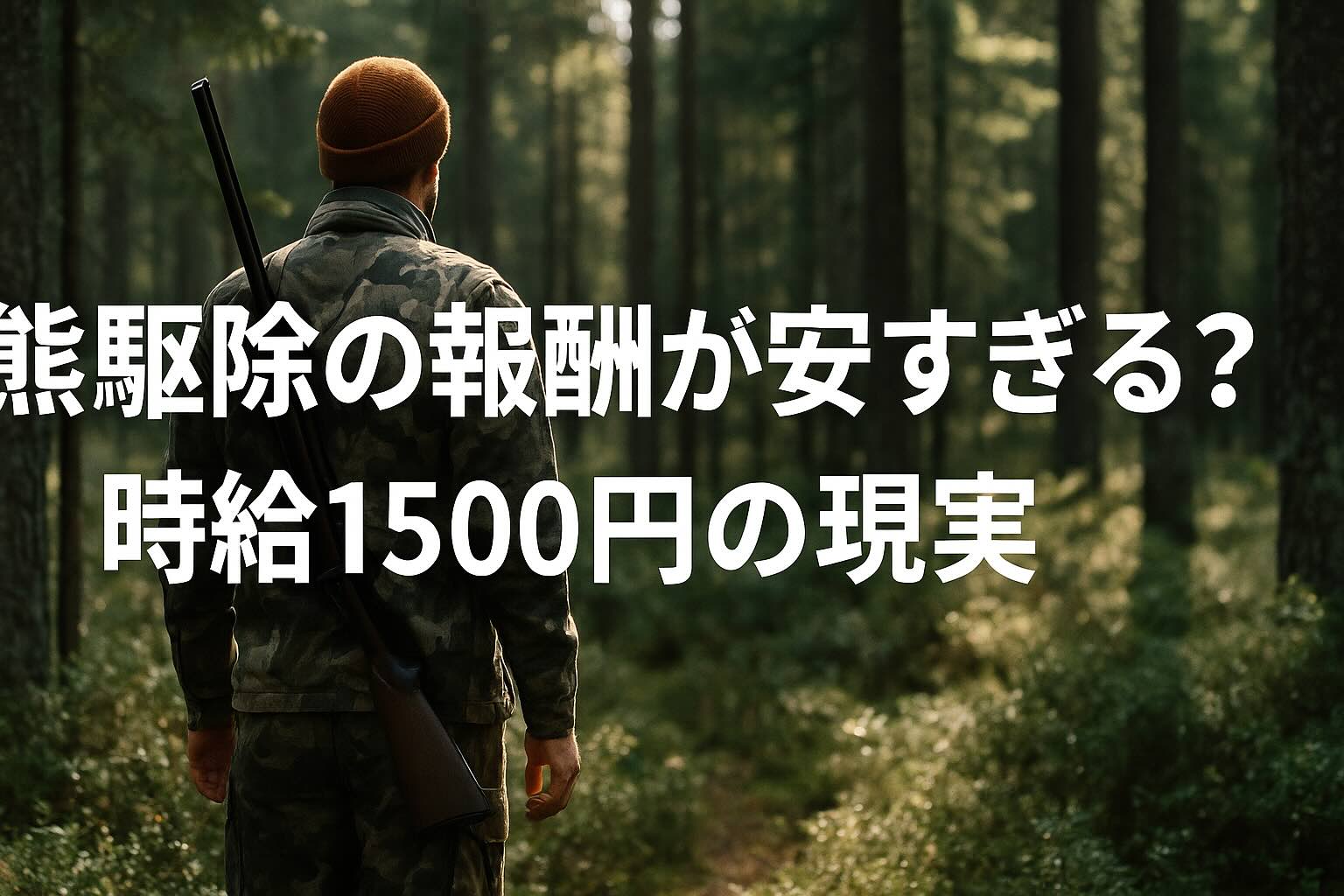
あまりにも安すぎる熊駆除の報酬に、驚いたことはありませんか?
命懸けで出動するハンターたちが受け取っている金額は、まさかの時給1,500円。
なかには弾薬代や交通費まで自腹というケースもあるのです。
この記事では、報酬の現実と各地の制度の違い、そして日本社会が抱える構造的な課題にまで踏み込んで解説します。
熊を駆除する仕事がなぜこれほど過小評価されているのか。
制度の裏にある“見えない不公平”とは何か。
この記事を読めば、その疑問がクリアになるはずです。
今、日本に必要なのは“命を守る人に光を当てること”。
ぜひ最後までお読みいただき、一緒に考えてみてくださいね。
熊駆除の報酬が安すぎる現実とは
熊駆除の報酬が安すぎる現実について、詳しく解説していきます。
①ハンターの命がけの仕事に1500円の時給
長野県で活動するハンターが、SNSで明かした報酬明細が大きな話題となりました。
クマ1頭あたりではなく、2時間3,000円、つまり時給にして1,500円の報酬だったのです。
この金額は、飲食店のアルバイトと同等か、それ以下の水準。
それなのに、相手は危険な野生動物であるクマ。命の危険と隣り合わせの作業にしては、あまりにも報酬が安すぎるという声が相次ぎました。
さらにこのハンターは「まあそれでもやるけどさ」と投稿しており、プロ意識を感じる一方で、その裏にある厳しい現実も垣間見えますよね。
命がけの仕事なのに、その労力に見合わない金額では、後継者不足にもつながりかねません。
この状況、どう考えても不公平に感じますよね……。
②弾薬代や装備費も自腹負担
この報酬問題、実は単なる金額の問題だけではありません。
クマ駆除に必要な弾薬代、トラップの設置費用、保険、車両のガソリン代など、多くのコストをハンター自身が負担しているのです。
たとえば、1回の出動で使う弾薬代だけでも数千円かかる場合があります。
それに加えて、狩猟免許の更新費用や年会費、安全講習費などの負担もあるんですよね。
時給1,500円をもらっても、経費を引けば実質は赤字というケースも。
まさに「ボランティアに近い」状態で、活動しているハンターも多いのです。
いや、もうこれ完全に持ち出しじゃん……って思ってしまいますよね。
③SNSで明かされた衝撃の報酬明細
この実情が広まったのは、X(旧Twitter)に投稿された実際の報酬明細の画像でした。
それによって、多くの人が「こんなに危険な仕事をしているのにこの金額!?」と衝撃を受けました。
この投稿は21万件以上の「いいね」を集め、多くの共感の声が寄せられています。
その中には、同業のハンターや元猟師からの「うちも同じようなもんだよ」といったコメントも。
問題は一部地域に限った話ではなく、全国的な構造的問題であることが明らかになってきました。
現場の声が可視化されたことで、社会全体がようやく「熊駆除報酬の問題」に気づき始めたのかもしれません。
④「やってられない」現場の声が続々
こうした状況に対して、現場のハンターたちからは「やってられない」という声が次々と上がっています。
「命を懸けて1頭数千円」「猟期外なのに呼び出される」「駆除しても感謝されないどころかクレームも」など、その声は悲痛です。
さらに、高齢化が進んでいるハンター業界では、担い手不足も深刻。
若い世代に継承されるためのインセンティブがなければ、いずれ駆除すらできなくなる可能性もあるのです。
「好きでやってるでしょ?」という無理解な声もありますが、好きだからこそ、正当な対価が必要なんですよね。
⑤牛丼バイトより安い?という指摘も
今回の報酬問題に対して、ネット上では「牛丼屋の深夜バイトより安いのはおかしい」との声が多数見られました。
実際、都市部の飲食店では深夜帯のアルバイト時給が1,600円~2,000円になることも珍しくありません。
それと比較して、クマ相手に命懸けで山に入る仕事が時給1,500円。
しかも、経費やリスクもまったく違いますよね。
「どっちがキケンかって聞かれたら…答えは明白ですよ」と、ハンターの1人は苦笑していたそうです。
これは笑いごとじゃないんですよ、本当に。
⑥報酬の安さがハンター離れに拍車
こうした報酬制度が続けば、当然ながらハンターになる人は減ります。
現に、新規の狩猟免許取得者は減少傾向にあり、既存のハンターも高齢化が進行中。
結果として、自治体は駆除要請があっても人員を確保できず、クマ被害が増加するという悪循環に陥っています。
まさに「安かろう悪かろう」で、人命を守る仕事が軽んじられているのが現状なのです。
⑦駆除依頼は増えるのに担い手が不足
近年、クマの市街地出没は増加傾向にあります。
環境省のデータでは、2025年度のクマによる死者はすでに前年比の2倍に。
にもかかわらず、駆除にあたる人員が確保できないという矛盾した状況が続いているのです。
これでは、ハンターにすべてを丸投げしているだけ。
社会全体で真剣に向き合うべき問題ですよね。
地域によって異なる熊駆除の報奨金制度
地域によって異なる熊駆除の報奨金制度について、事例をもとに掘り下げていきます。
①秋田市では出動報酬8000円に増額
秋田市では、クマの出没件数が急増した2025年度、緊急対策として猟友会員の出動報酬を4,000円から8,000円に倍増しました。
さらに、クマを実際に捕獲した場合には、1頭あたり1万円の報奨金が支給される仕組みも導入されています。
秋田市の対応は、ハンターの実情に配慮したものと言えるでしょう。
それでも、「命がけの仕事にしてはまだ安い」との声が上がっているのも事実です。
1回の出動が半日〜丸1日かかることを考えると、実質の時給は1,000円程度になるケースもあるそうです。
多少は改善されているとはいえ、危険手当としては心もとない金額ですよね。
②1頭1万円支給でも「命がけには安い」
たとえば、ツキノワグマの捕獲に成功したとしても、秋田市で支払われるのは1万円。
これはあくまで成功報酬のみであり、準備や移動、危険への対処を含めると、コストパフォーマンスは決して高くありません。
SNS上では「1万円って、事故でも起きたら完全に赤字じゃん」「命を危険にさらしてるのに安すぎる」との意見が多く見られました。
実際に、クマに襲われて大ケガを負ったハンターも全国で複数確認されています。
それでも、保険が適用されない場合や、治療費の自己負担が発生する場合もあるとのこと。
報酬が命のリスクに見合っていないという問題は、現場の共通認識になりつつありますね。
③ヒグマ駆除で日当8500円の奈井江町
北海道奈井江町では、ヒグマ駆除のハンターに日当8,500円を提示したことが報道され、波紋を広げました。
ヒグマといえば、日本に生息する野生動物の中でも最も危険性の高い種。
その捕獲や駆除において、たったの8,500円というのは、あまりにもリスクに見合っていないと感じる人が多いのは当然です。
「スズメバチ駆除ですら数万円なのに」といった比較もあり、地域による報酬設定のズレが明確になっています。
ハンターの善意と責任感に依存している制度の限界が、ここにも表れているように感じますね。
④キョン1頭3万円との報酬差に驚きの声
一方で、外来種の「キョン」に対しては、1頭あたり3万円という高額報酬が支給されている地域も存在します。
たとえば、茨城県つくばみらい市では、キョンを捕獲すると30,000円。
しかも、目撃情報を提供するだけでも2,000円の謝礼が出るとのこと。
この報酬額と比べて、クマの駆除に1万円、日当8,500円という設定は、完全に逆転現象と言えるでしょう。
対象の動物が違うとはいえ、命の危険度を考えれば、正当な評価が必要なはずです。
「命がけでやってる人がバカを見る」そんな構図になっていないか、しっかり見直してほしいですね。
⑤地域ごとの予算差と温度差の実態
なぜこれほどまでに地域差があるのでしょうか?
一因として挙げられるのが、自治体の予算と政策の優先順位の違いです。
都市部では財源が豊富な反面、山間部の町や村では限られた予算の中でやりくりせざるを得ません。
また、クマ被害の頻度や過去の事故件数などによって、危機感の温度差が生じていることも影響しています。
結果として、同じように危険な任務を担っていても、報酬制度には大きな開きが生まれてしまうのです。
「どこで駆除するか」によって、金銭的・制度的な扱いがこんなにも違うのは、やっぱりおかしいですよね。
⑥制度のばらつきが公平性に課題を生む
このような地域差によって、公平性の問題も浮き彫りになっています。
ある地域では3万円、別の地域では8,500円。
同じ命懸けの仕事なのに、これほどの差があるのは異常事態です。
しかも、報酬が低い地域ほどハンター不足が深刻化しており、負担が偏っているという悪循環にもつながっています。
全国統一の最低報酬制度や、政府の補助金制度などが必要とされる声も高まってきています。
「どこで働いても安心して報酬が得られる」そんな制度にしてほしいですね。
⑦地方自治体の工夫と限界とは?
もちろん、すべての自治体が怠慢なわけではありません。
秋田市のように報酬を倍増させたり、捕獲報酬を新設したりと、現場の声に耳を傾けているケースもあります。
それでも、財政面での限界に直面している自治体がほとんど。
また、制度改正には時間と手続きが必要で、緊急対応が難しいのも現実です。
地方自治体の創意工夫だけでは補えない部分を、国全体でサポートする仕組みが求められています。
「地域任せ」ではなく、「国ぐるみ」で命を守る社会づくりが必要なフェーズにきているのかもしれませんね。
熊駆除報酬の問題から見える日本社会の闇
熊駆除報酬の問題からは、日本社会の根深い構造的課題が浮き彫りになっています。
①「責任感」に依存する構造の問題
ハンターたちが危険な熊駆除に立ち向かう背景には、「人の役に立ちたい」「地域を守りたい」という強い責任感があります。
ところがその善意に、**行政が甘えすぎているのでは?**という指摘も出ています。
北海道奈井江町での「日当8,500円」提示も、「町のルールですので従ってください」といった姿勢が見られました。
まるで、「文句を言わずにやってくれるはずだ」と当然のように期待しているようにも見えてしまいますよね。
責任感が利用されている構造には、どこかモヤモヤを感じます。
②消防団やボランティアにも共通する構図
この問題は、熊駆除に限ったことではありません。
たとえば、消防団や災害ボランティアも、同様に「責任感」に依存して成り立っている側面があります。
彼らも非常時には命を懸けて人命救助を行いますが、報酬はごくわずか、または無償。
「地元だから」「助け合いだから」といった価値観が美徳として根付き、報酬や待遇の改善が置き去りにされがちなんですよね。
この「お金じゃないでしょ精神」が、日本全体に広がっているようにも感じませんか?
③「みんなのため」の精神が搾取を招く?
日本では、幼い頃から「みんなのために行動しよう」という教育が徹底されています。
もちろん、その精神は素晴らしいことです。
でも、それが過度になれば、個人の犠牲を当然とする社会構造にもつながってしまいます。
「自分の時間や命を使っても、地域のために頑張ってほしい」と求められる環境が、搾取の温床になっているのではないかと感じる人も増えています。
「正義感」がある人ほど損をする――そんな社会になってはいけませんよね。
④安全よりコスト優先の行政判断
自治体が報酬を抑えたがるのは、言うまでもなく予算の都合です。
しかし、安いコストで人命を守れるはずがありません。
にもかかわらず、「この金額でやってください」と言われると、現場は断れない空気に包まれてしまう。
そうなると、安全よりもコストが優先されてしまう状況に陥ってしまいます。
行政の仕事は「予算を守ること」ではなく、「住民の命を守ること」。
その原点を忘れてはいけないですよね。
⑤専門技術者への正当な評価が必要
クマを駆除するには、専門的な知識と高い技術が必要です。
猟銃免許の取得には講習、試験、実技、そして毎年の更新が必要。
その上、自然の中での危険察知能力や、迅速な判断力も求められます。
にもかかわらず、そうしたスキルが正当に評価されていない現実があります。
他の分野であれば、特殊技術者には高い報酬が支払われるのが常識。
なぜハンターだけが「責任感」でカバーしなければならないのでしょうか。
もっと、プロとしてリスペクトされるべき職業だと思いますよ。
⑥駆除のリスクと適正報酬をどう考えるか
クマ駆除は、人の命を守るための最後の砦とも言える存在です。
そのリスクの高さを考慮すれば、報酬は最低でも2万〜3万円は必要だと訴える専門家もいます。
また、精神的負担や家族への影響、怪我のリスクなど、金額には現れにくい負担も多いのです。
どこまでが「適正」かを考えるのは難しいですが、今の水準が適正とは到底言えないことは明白です。
国全体で「命の値段」をどう捉えるか、真剣に向き合うべき時期なのではないでしょうか。
⑦命を守るための仕組み再設計が急務
熊駆除に関する制度は、これまで自治体に大きく委ねられてきました。
しかし、全国でクマの被害が増加し、命が脅かされている今、国主導での仕組み改革が必要だという声が高まっています。
たとえば、
-
駆除報酬の最低ラインを全国統一
-
国からの特別交付金制度の創設
-
ハンター向けの保険・補助制度の整備
などが挙げられています。
命を守るために働いてくれる人が、ちゃんと報われる社会にしていきたいですね。
そのためにも、今こそ制度の再設計に踏み出すタイミングなのかもしれません。
まとめ
熊駆除の報酬があまりにも安いという問題は、単なる金額の話にとどまりません。
ハンターたちは命を懸け、危険な任務に挑んでいるにも関わらず、時給1,500円や日当8,500円といった報酬では割に合わないという現実があります。
地域によって制度の差も大きく、1頭あたり3万円の報奨金が出る外来種と比べても、熊駆除の待遇は著しく低いままです。
そこには、日本社会に根付く「責任感への依存」や「みんなのために我慢する文化」が影響しており、真の公平さが欠けています。
命を守る人に、適切な評価と報酬が支払われる社会を実現するためには、国全体での制度見直しが急務です。















