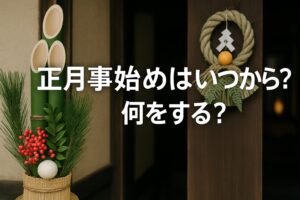冬至にかぼちゃを食べる意味を、子どもにもわかりやすく説明したい――。
そんなママやパパ、先生のために、この記事ではやさしく丁寧に解説していきます。
「どうして冬至にかぼちゃを食べるの?」「“ん”がつく食べ物ってなに?」といった素朴な疑問に、しっかり答えられるようになりますよ。
冬至の風習には、健康や幸せを願う昔の人の知恵がたっぷり詰まっています。
それを知ってから食べるかぼちゃは、きっともっとおいしく感じるはず。
子どもたちにも伝えたくなる、心があったかくなる内容をたっぷりご紹介します。
最後まで読めば、冬至の日に親子で楽しめるアイデアが見つかりますよ!
冬至にかぼちゃを食べる意味を子どもにわかりやすく解説
冬至にかぼちゃを食べる意味を、子どもにもわかるようにやさしく解説します。
寒い冬を元気に乗り越える知恵が、昔からこの習慣にこめられているんですよ~!
①冬至ってどんな日?
冬至は、一年の中で昼がいちばん短く、夜がいちばん長い日です。
12月の下旬(2025年は12月22日)にやってきて、冬の始まりの合図のような日でもあります。
この日を境に、少しずつ日が長くなるので「太陽が帰ってくる日」とも言われるんです。
昔の人にとって、寒さが厳しくなるタイミングでもありました。
だからこそ、「体を温めて、健康に冬を乗り切ろう」という願いをこめた行事が生まれたんですね。
子どもたちに説明する時は、「夜がとっても長い日だよ」「これから春に向かっていくんだよ」などと伝えると、イメージしやすいと思います。
ちょっとした豆知識をまじえると、「へぇ~!」となって興味を持ってくれるはずですよ。
②なぜ冬至にかぼちゃを食べるの?
冬至にかぼちゃを食べるのは、健康や長生きを願うためです。
昔は、野菜が少ない冬の時期に、保存がきくかぼちゃはとてもありがたい食べ物でした。
ビタミンやカロテンなどの栄養もたっぷり含まれていて、風邪予防にもピッタリなんです。
また、かぼちゃのオレンジ色は、太陽を思わせるあたたかい色。
太陽の力を体に取り入れるという意味もあるんですよ。
「なんで今日かぼちゃ食べるの?」と聞かれたら、「風邪ひかないようにするためだよ」「元気になれる食べ物なんだよ」と教えてあげてくださいね。
私も小さい頃、「かぼちゃを食べたら風邪ひかないよ~!」っておばあちゃんに言われたのを思い出します。
③「ん」のつく食べ物の意味とは?
冬至には、「ん」が2つつく食べ物を食べると運が上がるとも言われています。
たとえば、なんきん(かぼちゃ)、れんこん、にんじん、ぎんなん、きんかん、うどんなどがそうです。
これは「運盛り」と言って、「ん」が“運”につながると考えられていたんです。
つまり、「ん」のつく食べ物を食べることで、“運”を体にとりこむ、というわけなんですね。
子どもには、「“ん”がつくとラッキーになれるんだって!」とゲーム感覚で伝えても楽しいかも。
うちの子には「“ん”探しゲーム」やって盛り上がりました(笑)
④昔の人はどうしてかぼちゃを大事にしたの?
昔は、今みたいに冷蔵庫がなかったので、冬の間に野菜がとても不足しがちでした。
そんな中、かぼちゃは夏にとれても長く保存できるし、栄養もたっぷり。
冬に体調を崩さないための「自然のサプリメント」みたいな存在だったんです。
おばあちゃんの知恵や、先人たちの工夫が詰まった食材だったんですね。
今のようにスーパーに行けばなんでも手に入る時代とは違って、本当に大切な食べ物だったわけです。
「かぼちゃ=あたたかくてありがたい存在」だと伝えてあげると、子どもにもその価値が伝わると思いますよ。
⑤冬至の風習は日本だけ?
実は冬至の風習は、日本だけじゃなく世界中にあるんです。
たとえば中国では「餃子」を食べる風習があり、ヨーロッパでは太陽の復活を祝うお祭りがある地域もあります。
みんな「これから寒くなる冬を元気に乗り越えよう」と願って、いろいろな行事を行っているんですね。
世界の文化に触れることで、子どもたちの興味や視野も広がりますよ。
「ほかの国では何食べるのかな?」と一緒に調べてみるのも面白いです!
⑥子どもにどうやって伝えればいい?
子どもに伝えるときは、「食べ物」や「色」「音(“ん”)」など、五感を使って感じられる工夫をすると良いです。
例えば、「かぼちゃのあったかい色、太陽みたいだね!」とか、「“ん”がつくから運がよくなるんだよ」といった具合です。
紙芝居や絵本、冬至に関する歌やクイズも取り入れて、楽しく学べるようにするのがおすすめです。
私自身、子どもに話すときは一緒にかぼちゃを料理して、「なんできょうこれ食べるのかな~?」なんて会話しながら説明します。
やっぱり“体験”を通すと、記憶に残るんですよね!
⑦かぼちゃ以外に食べるといいものは?
さきほども出てきたように、「ん」がつく食べ物は運を上げるとされているので、いろんなものがあります。
| 食べ物 | 意味・理由 |
|---|---|
| なんきん(かぼちゃ) | 太陽の象徴、栄養豊富 |
| れんこん | 見通しが良くなる(穴が開いている) |
| にんじん | 体を温める |
| ぎんなん | 金運アップ |
| きんかん | のどに良い果物 |
| うどん | 長く生きる願いが込められる |
いろんな「ん」のつく食材を取り入れて、“冬至の運だめしメニュー”なんて作ってみると、子どもも喜びますよ~!
冬至にかぼちゃを食べる理由に関する参考情報
冬至にかぼちゃを食べる意味を、さらに深く理解するための情報を紹介します。
①冬至とかぼちゃの栄養的な関係
かぼちゃには、ビタミンA、ビタミンC、βカロテンがたっぷり含まれています。
| 栄養素 | はたらき |
|---|---|
| βカロテン | 免疫力アップ、風邪予防 |
| ビタミンC | 美肌、風邪予防 |
| 食物繊維 | お腹の調子を整える |
冬の寒さで体調を崩しがちなこの時期にぴったりの食材なんです。
②現代の家庭での冬至の楽しみ方
現代の家庭では、かぼちゃスープやかぼちゃの煮物、グラタンなどにして食べるのが人気です。
見た目もあったかくて、子どもでも食べやすいですよね。
食卓にちょっとした豆知識を書いたカードを置いたり、一緒に作ると楽しく学べます。
③保育園・小学校での伝え方アイデア
保育園や小学校では、紙芝居、絵本、ぬりえなどを活用するのがおすすめです。
たとえば「なんきんマン」というキャラクターを作って、「なんきんマンが風邪をやっつけるぞ~!」なんてお話にしても盛り上がります。
冬至やかぼちゃの基本情報・子ども向け豆知識
冬至やかぼちゃについての豆知識を、子ども向けに紹介します。
①冬至の時期と特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時期 | 毎年12月21日ごろ(2025年は12月22日) |
| 特徴 | 昼がいちばん短い日 |
| 意味 | 太陽の力が戻ってくるスタートの日 |
この日を境に少しずつ春へ向かっていきます。
②かぼちゃの種類と旬
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 日本かぼちゃ | 水分が多く煮物向き |
| 西洋かぼちゃ | ホクホク甘い、スープにぴったり |
| ペポかぼちゃ | ハロウィンの飾りにも使われる |
かぼちゃの旬は6〜8月ですが、冬にも保存して食べられるのが特徴です。
③子どもでも覚えやすい冬至のうたや遊び
子ども向けの「冬至のうた」や、「“ん”探しゲーム」「かぼちゃクッキング体験」などを取り入れると楽しい学びになります。
まとめ
冬至にかぼちゃを食べる意味には、昔からの知恵と健康への願いが込められています。
子どもにもわかりやすく伝えるには、「夜が一番長い日」「風邪をひかないようにするための食べ物」といったイメージを使うと良いでしょう。
“ん”のつく食べ物で運を呼び込む「運盛り」の習慣も、遊び感覚で楽しめます。
かぼちゃは栄養価が高く、寒い冬を元気に乗り切るのにぴったりの食材です。
世界にも冬至の風習があることを知ると、視野も広がりますよ。
おうちでの冬至イベントや、保育園・学校での伝え方の参考になれば嬉しいです。