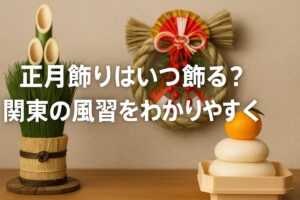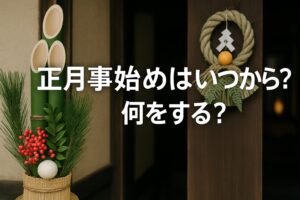成道会ってなに?という疑問を持つ子どもたちや保護者の方へ。
この記事では、成道会(じょうどうえ)の意味を子どもにもわかりやすく解説しています。
お釈迦さまが「さとり」を開いた大切な日である成道会は、仏教の行事の中でもとても重要な日。
でも、むずかしい話ではありません。
成道会を通じて、やさしさや感謝、そして心を落ち着けることの大切さを学ぶきっかけになります。
12月8日に行われるこの行事を、親子で楽しめる方法や、おうちでできる取り組みも紹介しています。
この記事を読むと、「なるほど、そんな意味があったんだ!」と感じられるはずです。
子どもにも伝えたくなる、心あたたまる仏教行事「成道会」を一緒にのぞいてみませんか?
きっと、毎年の12月が、もっとやさしい気持ちで過ごせるようになりますよ。
成道会の意味を子ども向けにわかりやすく解説!
成道会の意味を子ども向けにわかりやすく解説していきます。
どうして12月8日が特別なのか、どんな行事なのか、一緒に見ていきましょう!
①成道会ってどんな行事?
成道会(じょうどうえ)は、お釈迦さまが「さとり」をひらいた日をお祝いする仏教の行事です。
毎年12月8日にお寺などで行われていて、仏教の中でもとても大切な日とされています。
さとりを開いたことで、お釈迦さまは「仏さま」になったと考えられているんですよ。
日本全国のお寺では、この日になると特別な法要(ほうよう)やお話会、座禅などが行われたりします。
子どもたちにもわかりやすく伝えるために、紙芝居や絵本を使ったりするお寺もあるんですよ~!
②お釈迦さまは何をしたの?
お釈迦さまは、昔インドで王子として生まれましたが、世の中の苦しみや悲しみをなんとかしたいと思い、お城を出て修行の旅に出かけました。
たくさんの修行をしても答えが見つからなかったお釈迦さまは、ある日、菩提樹(ぼだいじゅ)という大きな木の下で静かに座って考え続けました。
そしてついに、心の平和や苦しみの原因と向き合い、「本当のこと」に気づいたのです。
これが「さとり」と呼ばれるもので、このときを記念して行われるのが成道会なんですよ。
③「さとり」ってどういうこと?
「さとり」とは、かんたんに言うと「ものごとの本当の姿を見抜くこと」なんです。
たとえば、ケンカしちゃったときに「自分が悪いんじゃないかな?」とか、「相手もつらい気持ちだったのかな?」って気づくこと、これも小さな“さとり”なんですよ。
お釈迦さまは、「人が苦しむのは、欲ばりな気持ちや思い通りにならないことから生まれる」と気づきました。
その気づきをもとに、人にやさしくしたり、自分の気持ちを大切にしたり、心を落ち着けることの大切さを伝えてくれたんですね。
④どうして12月8日に行うの?
12月8日は、お釈迦さまがさとりを開いた日とされています。
正確な日付はインドの暦(カレンダー)によって違うのですが、日本では昔からこの日を「成道の日」として大切にしてきました。
お寺では、この日を中心に法話(仏さまの教えをわかりやすく話す時間)や座禅会、精進料理(しょうじんりょうり)をいただくイベントなどが行われることもあります。
学校や家庭ではあまり知られていないけれど、仏教の大切な日として心を落ち着ける時間をもつのもいいですね。
⑤お寺ではどんなことをするの?
お寺では、成道会の日に次のようなことが行われます。
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 法要(ほうよう) | 仏さまに感謝をささげるためのお経をあげる時間 |
| 説法(せっぽう) | お坊さんが仏さまの教えについてお話する時間 |
| 座禅体験 | 静かに座って、心をととのえる体験 |
| 精進料理のふるまい | 肉や魚を使わず、体と心にやさしい食事をいただく |
| 子ども向け紙芝居や絵本 | むずかしいお話をやさしく楽しく伝える工夫 |
とくに最近では、子どもたちが楽しめるように、工作やぬり絵を取り入れたお寺もあるんですよ。
⑥学校や家庭でできることは?
学校や家庭でも、成道会にちなんだ小さな取り組みができます。
たとえば:
-
感謝の気持ちを手紙にして書いてみる
-
家族と一緒に静かに食事をして、話を聞く時間をつくる
-
欲しいものをグッと我慢してみる
-
心を落ち着ける深呼吸をしてみる
-
「ありがとう」や「ごめんね」を素直に伝える
このような行動が、実は「さとり」に近づく第一歩なんですよ。
⑦成道会から学べることって?
成道会からは、「心を見つめることの大切さ」「人へのやさしさ」「感謝の気持ち」など、今の時代にも通じる大切なことを学べます。
お釈迦さまのように、何かに気づいたり、考えたりする時間はとても貴重です。
日々の忙しさの中でも、「ちょっと立ち止まって考えること」の大切さを思い出させてくれますね。
成道会の意味を深める豆知識も紹介!
成道会の意味を深める豆知識も紹介します!
もっと知ると、成道会のことが好きになるかも?
①成道会の由来と歴史
成道会は、インドで始まった仏教の流れをくむ、日本独自の仏教行事のひとつです。
奈良時代から平安時代にかけて、日本の僧侶たちによって広められました。
その後、各宗派によって少しずつ形が変わりながらも、現在も12月8日を「さとりの日」として大切にしています。
仏教が日本に根付いた証でもある行事なんですね。
②世界の仏教イベントとの違い
実は、他のアジアの国では成道会を別の日に祝うこともあります。
たとえば、タイやスリランカでは「仏誕節(ぶったんせつ)」という別の祝日があります。
でも、日本では「成道会」として12月8日に行うのが特徴。
日本ならではの仏教文化がここにあるんですね。
③絵本や紙芝居での伝え方
子どもたちには、成道会を「お話」として伝えるのが効果的です。
おすすめの方法:
-
成道会を題材にした絵本を読む
-
お釈迦さまの人生を紙芝居で見る
-
保育園・幼稚園でイベントを開く
絵やお話を通して伝えると、子どもたちも自然と仏教の心に触れることができますよ。
成道会について子どもと話すためのヒント
成道会について子どもと話すためのヒントをまとめました。
家庭でも学校でも、ちょっとしたきっかけづくりに使ってみてくださいね。
①小学生でもわかる伝え方
「むずかしいことを考える日」ではなく、「やさしい気持ちを大事にする日」として伝えるとわかりやすいです。
たとえば、
-
「おしゃかさまが“本当に大切なこと”に気づいた日なんだよ」
-
「やさしさって、どうやって生まれると思う?」
-
「“ありがとう”を伝えるだけで、人の心ってあったかくなるよね」
こんな会話のきっかけがベストです!
②子どもの「なぜ?」に答えるコツ
子どもは「なんで?」をたくさん聞いてきます。
そのときは、正解を押しつけずに、こんなふうに返してみてください。
-
「なんでって思うよね。一緒に考えてみようか」
-
「おしゃかさまは、すごくいっぱい考えてたみたいだよ」
-
「どうしたら心が楽になるか、自分で気づいたんだって」
子どもの目線に合わせることがいちばんのコツです!
③親子で楽しめるおすすめの過ごし方
成道会の日には、親子でできる静かな遊びや、体験を楽しんでみましょう。
-
精進料理を一緒に作ってみる
-
一日スマホ・テレビお休みチャレンジ
-
お互いの「いいところ」を伝える時間を作る
-
お寺のイベントに出かけてみる
「心にやさしい1日」をテーマにすると、きっと素敵な日になりますよ。
まとめ
成道会は、お釈迦さまが「さとり」を開いたことをお祝いする仏教の大切な行事です。
毎年12月8日に行われ、心を見つめたり、人にやさしくすることの大切さを思い出させてくれます。
お寺では法要や座禅体験が行われ、子ども向けには紙芝居や絵本なども使ってやさしく伝えられています。
家庭でも、静かに過ごす時間や「ありがとう」を伝えることで、成道会の心にふれることができます。
親子で一緒に過ごすきっかけとして、成道会を取り入れてみてはいかがでしょうか。
子どもたちの「なんで?」にもやさしく答えながら、仏教のこころを伝えていけると素敵ですね。