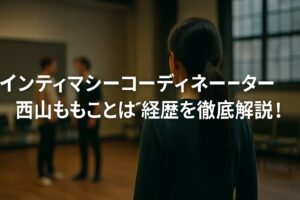「事実婚とは?」という疑問にやさしく、そして深くお答えします。
近年、結婚のカタチが多様化するなかで、婚姻届を出さずに夫婦のように暮らす「事実婚」という選択肢に注目が集まっています。
でも、事実婚って本当に法律的に大丈夫?
子どもができたらどうなるの?
周囲にどう伝えたらいいの?
そんな疑問や不安を抱えている方のために、事実婚の定義から、法律婚との違い、メリット・デメリット、実際に選んでいる人の声までをぎゅっとまとめました。
この記事を読めば、「自分らしいパートナーシップとは何か?」が見えてきますよ。
制度に縛られない、新しい関係の築き方を一緒に見つけていきましょう。
ぜひ、最後までじっくり読んでみてくださいね。
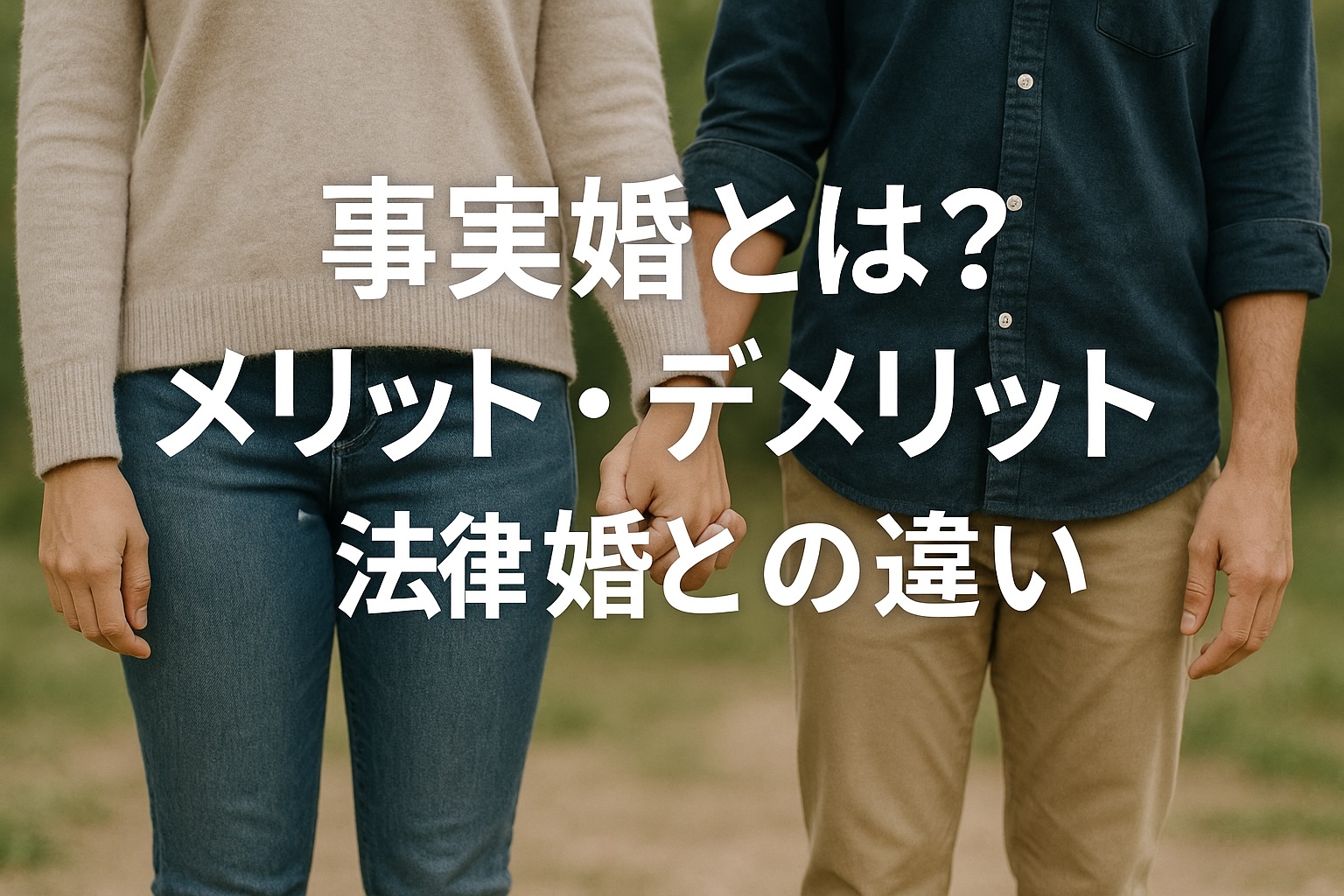
事実婚とは?法律婚との違いや定義をやさしく解説
事実婚とは?法律婚との違いや定義について、わかりやすく解説していきます。
①事実婚とはどういう関係?
事実婚とは、婚姻届を提出していないカップルが、夫婦として生活を共にしている状態を指します。
法律上の婚姻手続きをしていないため、戸籍上は「未婚」ですが、実際には夫婦同然の生活を送っているケースが多いです。
同居していて、生活費を分担したり、子どもを一緒に育てたりするなど、事実上の結婚生活を営んでいることから「事実婚」と呼ばれます。
よくあるパターンとしては、「制度に縛られたくない」「姓を変えたくない」「再婚に抵抗がある」などの理由で選ばれることが多いですね。
法律的な保護がないわけではありませんが、婚姻届を出していないため、税金や相続などの面で注意が必要です。
わたしの周りにも、事実婚を選んで幸せに暮らしているカップルがいて、とても自然な形だなと感じています。
②事実婚と法律婚のちがい
事実婚と法律婚の最大の違いは、「婚姻届を出しているかどうか」です。
| 比較項目 | 事実婚 | 法律婚 |
|---|---|---|
| 戸籍上の関係 | 他人 | 配偶者 |
| 姓 | 変える必要なし | 原則同じ姓 |
| 相続権 | 原則なし(遺言が必要) | 自動的に発生 |
| 税金の配偶者控除 | 原則対象外 | 対象となる |
| 社会保険の扶養 | 条件付きで可能 | 原則可能 |
| 子どもの嫡出性 | 非嫡出子 | 嫡出子 |
姓を変えたくない人や、自分の人生を自分で決めたいという人にとっては、事実婚はとても柔軟な制度です。
ただし、相続や税制の面では手間が増えるため、将来を見据えてしっかり準備しておく必要がありますよね。
③事実婚が選ばれる理由
最近では、若いカップルからシニア世代まで、さまざまな世代で事実婚を選ぶ人が増えています。
理由としては以下のようなものが挙げられます。
-
お互いの姓を変えたくない
-
再婚に抵抗がある
-
離婚歴があり、婚姻届にトラウマがある
-
家族や親戚との関係を避けたい
-
法律よりも自分たちのルールを重視したい
-
同性婚が認められていないための代替手段
わたしも正直、姓を変えることに強い違和感があるタイプで、「事実婚でもいいじゃん」と感じることも多いです。
形式よりも、二人の関係性を大切にしたいという価値観が、今の時代に合ってきてるんですよね。
④事実婚に必要な手続きはある?
事実婚には、婚姻届のような法的な書類提出は必要ありません。
しかし、以下のような手続きを行っておくと、法律上の保護が得やすくなります。
-
同居の証明(住民票の続柄を「未届の妻(夫)」に変更)
-
賃貸契約に連名で記載
-
医療同意のための委任状
-
保険の受取人指定
-
遺言書の作成(相続対策)
特に住民票を「未届の配偶者」にすることで、公的に事実婚関係を認められやすくなります。
こういった細かい工夫をしておくことで、いざというときにスムーズに対応できるんですよ~。
⑤事実婚で得られる法律的な保護
事実婚でも、すべての法的保護がないわけではありません。
長期間の同居や生活の共有が認められれば、以下のような保護が可能になります。
-
損害賠償の請求(浮気された場合など)
-
財産分与
-
扶養義務
-
社会保険の扶養(条件付き)
-
子どもの認知と養育費請求
ただし、法律婚に比べて、証明が必要なケースが多いため、日頃から記録を残しておくことが大切です。
トラブルを未然に防ぐために、事実婚契約書などの作成も検討しておくと安心ですよね。
⑥事実婚で子どもはどうなる?
事実婚カップルに子どもが生まれた場合、**婚外子(非嫡出子)**となります。
これは戸籍上、父親が自動的に認知されるわけではないため、父親が認知届を提出する必要があります。
認知されることで、子どもは父親の子として法的に認められ、養育費請求や相続権が発生します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 子の戸籍 | 母の戸籍に入る(父の認知が必要) |
| 嫡出子との違い | 相続の順位は同じ(差別は廃止済) |
| 父親の責任 | 認知+養育義務が発生 |
現代では、非嫡出子であっても法律上は平等に扱われますが、手続きが必要なのは覚えておきたいポイントですね。
⑦同性カップルと事実婚の関係
日本では現在、同性婚は法律上認められていません。
そのため、同性カップルが共同生活を営む場合、事実婚に近い状態で暮らすことになります。
自治体によっては「パートナーシップ制度」を導入しており、病院での面会や住居契約などで一定の法的効力が認められることもあります。
-
渋谷区や世田谷区などで導入
-
公営住宅の入居が可能になる自治体も
-
保険の受取や医療同意がスムーズになるケースも
法整備が追いついていない現状では、事実婚という形が、同性カップルにとっても大切な制度のひとつとなっていますよね。
事実婚のメリット・デメリット
事実婚のメリット・デメリットをリアルに紹介していきます。
①事実婚のメリット
事実婚には、法律婚にはない自由さや柔軟さがあると言われています。
以下に代表的なメリットをまとめました。
-
姓を変える必要がない
-
離婚時の手続きが不要(婚姻届を出していないため)
-
相手の戸籍に入らず、自分の家族関係を保てる
-
法制度よりも、自分たちの関係性を重視できる
-
再婚や年齢差カップル、同性カップルにも適している
特に「姓を変えなくていい」というのは、女性にとって大きなメリットだと感じます。
結婚のために仕事の名前を変えたり、手続きが山ほどあるって…ちょっと負担が大きいですもんね。
自由を大事にしたい人や、柔軟なパートナーシップを望む人には、すごく合ってる形だと思います。
②事実婚のデメリット
一方で、事実婚には不便さやリスクも存在します。
以下が代表的なデメリットです。
-
相続権が自動的に発生しない(遺言がないと財産がもらえない)
-
配偶者控除などの税制上の優遇が受けられないことがある
-
周囲に理解されにくいことがある(家族や親族との関係)
-
子どもの戸籍・認知に手続きが必要
-
引越しや入院などの手続きで苦労することも
特に将来的な介護や相続の話になると、「やっぱり法律婚のほうが…」と思う場面もあるかもしれません。
法律的には「他人」のままなので、慎重に準備しておかないと不利益を受けることもあります。
筆者としては、**事実婚を選ぶなら“事前の備え”が命!**だと声を大にして言いたいです。
③筆者の考える「事実婚」の向き・不向き
正直に言えば、事実婚が向いている人と、そうでない人がいると思います。
筆者なりに考えてみると、こんな特徴の人に事実婚は合っています。
向いている人
-
自由や個性を大事にしたい
-
法律や制度に縛られたくない
-
家族や世間の価値観に流されたくない
-
パートナーと対等な関係を築きたい
向いていない人
-
法律的な安定や保障を求めている
-
相続や税制の優遇を重視する
-
家族や親戚との関係性が強い
-
子どもを生み育てる前提での結婚を考えている
わたしの感覚では、事実婚は“心の距離が近い”からこそできるスタイルだと思うんですよね。
制度で守られていない分、信頼関係が何よりも大切です。
④実際に事実婚している人の声
最近はSNSやメディアでも、事実婚カップルのリアルな声がたくさん見られるようになりました。
以下はよく聞く意見です。
-
「姓を変えずに済んだことで、自分らしさを保てた」
-
「夫婦という感覚はあっても、書類に縛られていないのが心地いい」
-
「周囲の理解がないと、少し苦労する場面もあった」
-
「子どもの手続きが面倒だったけど、それ以外は満足」
-
「“離婚”の概念がないので、逆に関係が長続きする気がする」
こうした声を聞くと、「結婚=婚姻届」という価値観にとらわれなくていいのかも、と思えますよね。
生き方が多様化する今、こういう選択肢があるのは本当に素敵だと思います。
⑤芸能人・有名人の事実婚エピソード
実は、事実婚を選んでいる芸能人・有名人もたくさんいます。
代表的なカップルをいくつかご紹介します。
| 名前 | パートナー | コメント |
|---|---|---|
| 内田裕也 & 樹木希林 | 事実婚のまま生涯を共にした | 「夫婦ってこういう形もあるんだ」と話題に |
| YOU & 元旦那 | 再婚後は事実婚状態に | あえて届を出さないスタイル |
| 宮本亜門 | 同性パートナーとの生活 | 自由でオープンな関係を公言 |
こうした人たちを見ると、「結婚=婚姻届」という固定観念に縛られなくていいんだなと勇気をもらえます。
芸能人に限らず、私たちももっと自分らしいパートナーシップを築いていい時代ですよね。
事実婚を考える人へのアドバイスまとめ
事実婚を考える人へのアドバイスを、リアルな視点でお届けします。
①事実婚前に確認すべきこと
事実婚を始める前に、絶対に話し合っておきたいポイントがいくつかあります。
-
お互いの価値観・結婚観は合っているか
-
子どもを持つかどうかについての考え
-
財産管理や生活費の分担はどうするか
-
姓や戸籍への希望
-
老後や介護、万一のときの対応方法
事実婚は、制度的なサポートが弱い分、最初のすり合わせがとても重要です。
「好きだから大丈夫」と思って始めても、法律で守られていないことで後々モヤモヤすることもあるんです。
書類はなくても、“言葉と信頼”でしっかり確認し合うことが、事実婚の第一歩ですよ〜。
②事実婚を継続するための工夫
事実婚を長く続けるには、ちょっとした工夫とお互いへの思いやりがカギになります。
以下のような工夫をしているカップルが多いです。
-
お金の管理ルールを明確にする(共通財布 or 割り勘)
-
定期的に“話し合いの日”を設ける
-
同居契約書や事実婚契約書を作る
-
住民票の「続柄」を「未届の妻・夫」にしておく
-
共通口座をつくってライフプランを共有する
特に、書面での取り決めは「いざというとき」の安心材料になります。
制度に頼れないからこそ、自分たちでルールを作る姿勢がすごく大切だと思うんです。
私の知人で事実婚10年続いてるカップルがいますが、「定期的に手紙を書いてる」って言ってて、素敵だな~って思いました!
③周囲への伝え方・トラブル回避のコツ
事実婚を選んだとき、意外と難しいのが“周囲への説明”。
とくに親世代や職場など、理解が得られないこともありますよね。
以下のような工夫が役立ちます。
-
「自分たちなりの夫婦のかたち」と前向きに伝える
-
あえて法律婚と比較しないで、自然体で説明する
-
住民票などの書類を見せて“公的な証拠”を提示する
-
職場の福利厚生や手続きを調べておく
-
子どもや相続についても、親と話し合う時間を持つ
“理解してもらおう”というよりも、“誠意をもって共有する”ことが大切です。
私自身も、最初は「え、結婚しないの?」って言われるだろうな〜と思ってましたが、しっかり理由を伝えたら意外とすんなり受け入れてもらえました。
世の中も少しずつ変わってきているんですね!
まとめ
事実婚とは、婚姻届を提出せずに夫婦同然の生活を送るパートナーシップのかたちです。
法律婚とは異なり、姓を変えずに済むなどの自由さがある一方で、相続や税制面での注意点も存在します。
現代では多様な価値観に基づいて、あえて事実婚を選ぶカップルが増えており、同性カップルや再婚を望まない人にも支持されています。
ただし、法的な保護を受けるためには住民票の記載変更や契約書の作成など、一定の備えが必要です。
身近な芸能人やリアルな事例からも分かるように、「届け出」よりも「信頼関係」を重視した新しい生き方が広がっています。
自分たちにとって何が一番自然で幸せなのか、一度立ち止まって考えることが大切ですね。