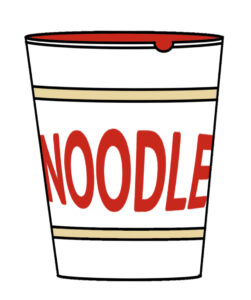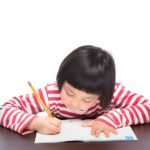「え、それ本当?」
SNSで見かけたニュースや噂に、そんな疑問を抱いたことはありませんか?
今や、誰でも情報を発信できる時代。だからこそ“正しい情報を見抜く力”が必要です。
この記事では、ネット上の偽情報に立ち向かう専門機関「日本ファクトチェックセンター(JFC)」について、編集長の古田大輔の経歴とともに詳しく紹介します。
JFCの設立目的、資金源、中立性の維持、そして実際の活動内容まで、読者が気になるポイントをまるっと解説!
読めば、「どうやってデマを見抜くか」「自分の身を守るには何が必要か」がスッキリ分かりますよ。
さらに、教育現場での取り組みや、海外との比較などの情報も集めました。
選挙の投票先、皆さんはどのメディアを参考に決めていますか?
▪️投票先を考えるための3ステップ
▪️投票先を決める際に参考になる情報源一覧と特徴
日本ファクトチェックセンター編集長の古田大輔さん(@masurakusuo)に解説してもらいました📝https://t.co/rcrKAvvA2D— 新聞科学研究所 (@np_labo) June 18, 2025
Contents
古田大輔ってどんな人?
SNSでデマを見抜く力を伝える上で、名前がよく登場するのが古田大輔という人物です。
日本ファクトチェックセンターの編集長を務め、信頼できる情報を見極めるための取り組みを全国に広げています。
この記事では、古田大輔の経歴や実績、どんな価値観を持つ人なのかを紹介します。
次の項目では、彼がこれまでに関わってきた大手メディアやプロジェクトにも触れていきます。
ジャーナリストとしての経歴と実績
古田大輔は福岡県出身のジャーナリストで、早稲田大学政治経済学部を卒業後、朝日新聞に記者として入社しました。
国内の支局で経験を積んだあと、アジアの国際報道にも関わり、シンガポール支局長まで務めた実績があります。
その後、2015年にBuzzFeed Japanの創刊編集長としてデジタルメディアの最前線に立ち、フェイクニュースや社会問題を積極的に報じて話題を集めました。
2019年には独立し、メディアのコラボレーション支援を行う「株式会社メディアコラボ」を設立しています。
記者としての経験に加え、発信力・教育力も評価され、Google News Labの講師や、情報リテラシー教育の分野でも活躍中です。
日本ファクトチェックセンターの設立目的は?
SNSやネットニュースが当たり前になった今、誤った情報が簡単に広がってしまう時代になっていますよね。
そんな中で、日本ファクトチェックセンター(通称JFC)は「正しい情報」を広めるために設立されました。
ここでは、JFCがなぜ作られたのか、どんな背景があるのかを分かりやすくまとめていきます。
次は、設立の根本にある“社会課題”について見ていきますね。
なぜ今ファクトチェックセンターが必要とされたのか
設立のきっかけは、SNS上で急速に広まる“デマ”の深刻さです。
選挙やコロナ、災害など社会的に大事な場面で、間違った情報が拡散されるケースが増え、多くの人が混乱してしまいました。
こうした状況を受けて、ネット上の情報を「正しく検証する仕組み」が日本にも必要だと考えられたのが始まりなんです。
特に2020年代に入り、生成AIの登場でフェイクコンテンツの質も高くなり、もはや素人では見抜けないレベルになってきました。
こうした危機感の中で、JFCは2022年に誕生しました。
誰が資金提供してるの?利害関係はないの?
ファクトチェックって中立性が大事だからこそ、誰が資金を出しているのか気になりますよね。
ここでは、日本ファクトチェックセンター(JFC)の資金提供元や、そこに利害関係がないのかについて解説していきます。
GoogleやYahoo!からの資金提供
JFCの立ち上げには、GoogleとYahoo! Japanが大きく関わっています。
具体的には、Googleが約150万ドル(2億円超)という規模の資金提供を行い、Yahoo!も運営支援をしています。
この資金は、運営費だけでなく、ファクトチェックに必要な調査費・スタッフの人件費・教育コンテンツの制作費などに使われているようです。
JFCはこのような支援を受けつつも、「編集には一切関与しない」という契約を交わしており、出資企業がコンテンツに口出しできない体制が整えられています。
つまり「お金は出すけど、口は出さない」というスタンスなんですね。
出資に対する懸念と透明性への取り組み
とはいえ、大企業からの支援があると「本当に中立なの?」と心配になる人も多いと思います。
そのためJFCでは、透明性を保つために出資元や編集体制を公式サイトでしっかり公表しています。
さらに、NPOや大学研究者、ジャーナリズム団体などの第三者とも連携しながら運営することで、バランスのとれたチェック体制を実現しています。
こうした取り組みで、ファクトチェックの信頼性を保つ工夫がされているんですね。
中立性や信頼性はどう担保されてる?
ファクトチェックって「信じていいの?」と思う人も多いですよね。
そのため、日本ファクトチェックセンター(JFC)は、中立性と信頼性をとても大事にしています。
ここでは、JFCがどんな体制や工夫で中立性を保っているのか、具体的に見ていきます。
次の見出しでは、実際のファクトチェック方法についても紹介します!
編集方針と第三者チェック体制
JFCでは、記事を出す前に「編集会議」で内容の妥当性をしっかり確認する体制をとっています。
情報の出典や根拠を示すのはもちろん、判断の過程も明示するスタイルなので、読者も「どうやって結論に至ったか」が分かりやすいです。
また、複数のジャーナリストや研究者が関わっていて、一人の判断だけに頼らないチーム体制も大きな特徴です。
GoogleやYahoo!といった出資企業とは「編集には一切介入しない」という契約を交わしていて、独立性も守られています。
このように、透明なプロセスと第三者の視点で中立性が担保されているんです。
誤解を防ぐためのルールやポリシー
JFCでは、記事ごとに「ファクトチェックの分類」や「判定理由」を明記しています。
例えば、「誤り」「一部誤り」「根拠不明」などの評価項目を設け、どの程度の誤りなのかも読者に伝わるように工夫されています。
さらに、読者からの指摘や反論にも対応する窓口を設けているのもポイント。間違っていたら訂正するという誠実な姿勢が信頼感につながっています。
このような取り組みで、「ただの主張」で終わらせずに、事実に基づいた情報提供を目指しているんですね。
どうやって情報を見極めるの?
SNSで見かけたニュース、どれが本当でどれがウソなのか…。
そんな疑問に応えてくれるのが、日本ファクトチェックセンター(JFC)のファクトチェック手法です。
ここでは、JFCが実際にどんな方法で情報を見極めているのか、そして私たち一般人にもできる見抜き方を紹介します。
次は、実際にJFCがやっている活動内容にも触れていきますね。
JFCが実践しているファクトチェック手法
JFCではまず、SNSやネットで拡散されている話題の情報を常にモニタリングしています。
次に、「その情報に対して社会的影響があるか?」を判断し、優先度の高いものからチェックに入ります。
チェックの過程では、一次情報(公的資料・元の発言・専門家の見解など)に基づいて検証を行います。
検証結果は「正確」「一部誤り」「誤り」「根拠不明」などの評価付きで公開され、誰でも確認できるようになっています。
内容だけでなく、情報がどう伝わったかという文脈や切り取り方の影響も重視して分析しているのが特徴です。
一般人でもできる情報の見極め方
JFCのような専門機関でなくても、実は私たちにもできるファクトチェックの第一歩があります。
例えば…
-
複数の信頼できるニュースソースと照らし合わせる
-
情報の出どころ(一次情報)を探す
-
タイトルと本文で内容が一致しているか確認する
-
感情をあおる言葉が使われていないか冷静に見る
こうした視点を持つだけでも、デマに惑わされるリスクはぐっと減ります。
JFCの活動って具体的に何してるの?
ファクトチェックって言葉はよく聞くけど、実際にどんなことをしてるのかって気になりますよね。
日本ファクトチェックセンター(JFC)は、ただ情報の真偽を調べるだけじゃなく、いろんな形で社会に貢献しています。
ここでは、JFCが日々どんな活動をしているのか、具体的な内容や実例を紹介します。
次のパートでは、JFCを支援するGoogleやYahoo!との関係にも触れていきます!
ネット上の情報をチェックする流れ
JFCがまず行っているのは、SNSやネットニュースなどの情報監視(モニタリング)です。
話題になっている情報や、「これ本当なの?」と疑問を持たれやすい投稿をピックアップします。
その後、専門家や編集チームがリサーチ・分析を行い、情報の正確性を検証します。
その結果を「ファクトチェック記事」としてJFC公式サイトやYahoo!ニュースなどで公開しています。
この一連の流れは、透明性が保たれていて、記事ごとに「判定理由」や「出典」がしっかり記されています。
具体的なチェック事例とその影響
実際にあったチェック事例のひとつに、「大物政治家が不正献金を受け取った」というSNS上の投稿があります。
この投稿は事実に基づかないもので、JFCが一次資料を元に「誤り」と判定したことで、多くの拡散が抑制されました。
他にも、健康情報、災害時の誤報、コロナ関連の誤情報なども多数チェックされ、混乱防止に役立っています。
さらに、学校や企業に向けたワークショップや教材提供も行っており、情報リテラシー教育にも力を入れているんです。
GoogleやYahoo!の関わりって?
JFCの話をするときに欠かせないのが、大手IT企業の関与です。
「えっ、GoogleやYahoo!って運営に関わってるの?」と驚く人もいるかもしれません。
ここでは、JFCの設立や運営にどんなふうにGoogleとYahoo!が関わっているのかを解説します。
次の項目では、SNS上での偽情報の深刻さについても紹介していきます!
JFCの立ち上げに関わった企業とは?
日本ファクトチェックセンターの設立には、GoogleとYahoo! Japanが深く関わっています。
2022年の発足時、Googleは約150万ドル(約2億円以上)を提供し、Yahoo! Japanも技術面や告知面での協力を行いました。
JFCの公式記事はYahoo!ニュースなどで配信されることも多く、ユーザーへの情報提供がより広く届く仕組みになっています。
ただし、両社は「編集には関与しない」ことを明言しており、報道の中立性を守るためのルールがしっかり決められています。
メディアとプラットフォームの協力関係
このような企業とファクトチェック団体の協力は、海外ではすでに広く行われていて、日本でもようやく本格的にスタートした形です。
SNSや検索エンジンが情報流通の中心になっている今、プラットフォーム企業が「正しい情報を届ける」責任を果たそうとしている流れなんですね。
特に、Google News Initiativeなどのプロジェクトを通じて、ファクトチェック支援や教育活動も積極的にサポートしています。
SNSの偽情報ってどのくらい深刻?
「SNSで見たあの情報、ほんとかな…?」と思ったこと、誰でも一度はありますよね。
実はその“あやしい投稿”、多くの人に広がって社会的な影響を与えているかもしれません。
このパートでは、SNSにおける偽情報の深刻さや、実際に起きた問題事例について解説していきます。
次は海外と日本のファクトチェック体制の違いについても見ていきますね。
国内外の実例と拡散のメカニズム
たとえば、2021年の衆議院選挙では「野党候補が外国人に投票権を与えると発言した」という事実無根の情報がX(旧Twitter)で拡散しました。
この投稿はリツイートや引用で広がり、数日で数万件のインプレッションを記録。
最終的に、JFCが調査し「そのような発言は一切確認されなかった」と発表するまで、多くの人が誤解したままでした。
他にも、コロナワクチン関連の誤情報や、災害時のフェイク画像なども頻繁に流通しており、社会不安の原因になることもあります。
SNS運営側の対策とその限界
X(旧Twitter)やFacebook、Instagramなどの運営会社も、偽情報対策に力を入れ始めています。
たとえば、「注意」ラベルを付けたり、信頼できる情報源を表示したりする工夫が行われています。
ただし、AIによる自動検出には限界があり、人の手によるチェックがまだまだ必要な状況です。
特に日本では英語圏に比べて、対応が遅れていた面もあり、JFCのような機関が果たす役割はますます重要になっています。
次は「海外と日本のファクトチェック体制の違いは?」をテーマに、世界との比較をしてみましょう!
海外と日本のファクトチェック体制の違いは?
「日本ってファクトチェックが遅れてる?」
そんな疑問を持つ人も増えています。
このパートでは、アメリカやヨーロッパのファクトチェックの体制と、日本の現状を比べながら紹介します。
次は、教育の現場での取り組みについても詳しく見ていきますね!
欧米諸国との比較で見える課題
アメリカやイギリスなどでは、2016年の米大統領選をきっかけにファクトチェックの必要性が高まり、多くの団体が誕生しました。
「PolitiFact」「Snopes」「Full Fact」などの団体は、数十人規模のスタッフを抱え、政治・医療・教育など幅広い分野をカバーしています。
これに対して、日本は長らく「メディア側の自己判断」に任されてきた部分が多く、組織的なファクトチェックは2020年以降ようやく本格化した状況です。
JFCができたことで体制は整いつつありますが、まだ人員や予算面では小規模で、欧米に比べてカバー範囲が限られているのが現実です。
日本の改善ポイントと可能性
一方で、日本ならではの良さもあります。
たとえば、JFCのファクトチェック記事はYahoo!ニュースで広く拡散される仕組みがあり、短期間で多くの人に届きやすいんです。
また、教育現場と連携して「情報の見極め方」を教える機会も増えており、次世代に向けたリテラシー教育が広がってきているのも希望の光です。
今後は、自治体や大学、他のメディアとも連携しながら「日本ならではのファクトチェック文化」が育っていく可能性がありますよ。
学校での教育に取り入れられているの?
SNSやネットが当たり前の時代、子どもたちが早いうちから「情報の見極め方」を学ぶことはとっても大切です。
日本ファクトチェックセンター(JFC)は、そんな教育現場にも関わり始めています。
このパートでは、JFCがどんな形で教育に携わっているのか、実際の取り組みや今後の展望についてまとめます。
メディアリテラシー教育の現状
JFCでは、全国の学校や大学に向けて「メディアリテラシー教育」のプログラムを展開しています。
たとえば、「このニュースは本当に正しい?」と問いかけるワークショップを実施し、生徒自身が情報の信ぴょう性を考える授業が行われています。
実際に、先生や学生がJFCのファクトチェック記事を使ってディスカッションをする事例も増えているそうです。
また、大学では「デジタル・ジャーナリズム」や「報道倫理」の授業の中に、JFCが制作した教材が取り入れられることもあります。
学生が受けられるファクトチェック教育の実例
高校や大学だけでなく、小学生向けにも「ネット情報との向き合い方」をテーマにした講座が行われています。
たとえば、「うそニュースにだまされないコツ」や「SNSで注意すべき言葉の見分け方」など、子どもでも実践しやすい内容になっているのが特徴です。
さらに、教師向けの研修プログラムも用意されており、学校全体でファクトチェック意識を高める取り組みが進んでいます。
このように、JFCの活動は「今の社会」だけじゃなく、「未来の社会」にもちゃんと目を向けているんですね。
よくある質問(Q&A)
Q: 日本ファクトチェックセンター(JFC)はどんな団体なんですか?
A: JFCはSNSやネットで拡散される偽情報を検証し、正しい情報を広めるために設立された組織です。GoogleやYahoo!が支援しつつも、編集内容には関与せず、中立性を保っています。
Q: JFCはどうやって情報の正しさをチェックしているの?
A: 一次情報や公的資料、専門家の見解をもとに、編集チームと専門家が検証しています。検証結果は「誤り」「一部誤り」などの評価付きで公開されます。
Q: 誰がJFCにお金を出してるの?偏りはないの?
A: 主にGoogleとYahoo! Japanが資金提供していますが、編集には一切関与しない契約があり、出資と報道内容の独立性は分けられています。
Q: 一般人でもファクトチェックってできるの?
A: できます。複数の信頼できるソースで確認したり、情報の出どころを調べたり、あおり文に惑わされないよう冷静に見ることが大切です。
Q: 日本のファクトチェックは海外に比べてどうなの?
A: 欧米に比べて体制や規模は小さいですが、JFCを中心に体制が整い始めています。Yahoo!ニュースとの連携や教育現場への展開など、日本独自の強みも出てきています。
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。
-
古田大輔は、朝日新聞・BuzzFeed Japanなどで活躍した経験豊富なジャーナリスト
-
日本ファクトチェックセンター(JFC)は、ネット上の偽情報を検証するために設立された団体
-
GoogleとYahoo!が資金提供しているが、編集には関与しておらず中立性は保たれている
-
SNSの偽情報は選挙や健康などにも影響を与えるほど深刻
-
JFCは情報を検証し、チェック結果を公開するだけでなく、教育現場への展開も進めている
-
海外に比べて日本の体制はまだ成長途中だが、独自の取り組みが期待されている
この記事を読んだことで、JFCの信頼性や必要性、そして自分で情報を見極める大切さがよく分かったと思います。
ぜひこれからは、SNSやニュースに触れるときは「この情報は本当に正しいのか?」という視点を持ってチェックしてみてくださいね。